ヘルスケア業務

ヘルスケア業務として、医療法務(医療法人、診療所、クリニックなど)や薬機法(薬局、医療機器)、毒物・劇物について対応します。
料金(報酬)は、同ホームページ内にありますので、確認願います。![]()
1 医療法務(医療法)
〇 医療法務の核心:「事後対応」から「予防と手続き」へ
医療機関における「法務」と聞くと、多くは患者との医療トラブルや職員との労務紛争、損害賠償請求といった、問題発生後の「事後対応」を想起しがちです。
これらは弁護士が主役となる領域ですが、医療法人やクリニックの持続的な運営において、より根源的に重要なことは、トラブルの発生を未然に防ぐ「予防法務」と、法令遵守のための「手続き法務」です。
実際に多くの医療機関では
・医療法人設立後に、毎年提出が義務付けられている事業報告書を提出していなかった。
・診療所の構造を一部変更した際に、保健所への届出を失念していた。
といった手続き上の不備が原因で、後日、行政から指導を受け、問題が表面化するケースが後を絶ちません。
このような、日々の運営における法務手続きを専門的に支援するのが行政書士です。
行政書士は、医療機関と行政(県庁、保健所、厚生局など)との間に立つ“橋渡し役”として、運営の根幹に関わる書類作成と許認可申請を担う、「医療現場の法務担当者」と言える存在です。
〇 行政書士が支援する具体的な医療法務業務
行政書士が担う役割は、医療機関の日々の運営に密着した、極めて実務的なものです。
以下にその代表的な業務を挙げます。
1 医療法人の設立・運営に関する手続き
医療法人の根幹を支える定款や議事録、各種届出を法的に不備なく整備します。
⑴ 設立時:
法人の憲法となる「定款」、出資財産の明細である「財産目録」、設立時の意思決定を示す「社員総会議事録」など、設立認可申請に必要な一連の書類を正確に作成します。
⑵ 運営時:
役員(理事・監事)の変更に伴う「役員変更届」、事業年度終了後に提出が義務付けられている「事業報告書」「決算報告書」、社員総会や理事会の「議事録」の作成と整備を支援します。
これらを怠ると、行政指導の対象となる可能性があります。
2 診療所の開設・変更・廃止に関する手続き
診療所のライフサイクルに伴う、保健所等への手続きを代行します。
開設・移転:分院展開やクリニックの移転に伴う保健所への「開設許可申請」「開設届」、および旧診療所の「廃止届」の作成と提出を支援します。
〇 内容変更:
診療所の構造設備(例:レントゲン室の増設)や管理者(院長)の変更時に必要な「許可事項一部変更許可申請」や届出を適切に行います。
3 医療広告ガイドラインの遵守支援
ウェブサイト、チラシ、看板などの広告物が、厚生労働省の定める「医療広告ガイドライン」に違反していないかをチェックします。
⑴ 表現の確認:
「最高の治療」「絶対安全」といった誇大広告や、患者を誤認させる可能性のある表現がないかを確認します。
⑵ リスク回避:
違反が指摘されると、行政指導や改善命令、最悪の場合は罰則の対象となります。
特に新規開設のクリニックで見落とされがちなリスクを未然に防ぎます。
4 附帯業務の開始手続き
医療法人が介護事業など、定款で定められた本来業務以外の「附帯業務」を開始する際に必要となる「定款変更認可申請」を支援します。
5 他の専門家(士業)との役割分担と連携
医療法務は、各分野の専門家が連携することで、最も効果的なサポート体制が実現します。
⑴ 弁護士:紛争解決の専門家
・具体的な業務:
患者との医療トラブル、職員との解雇などを巡る労務紛争、損害賠償請求への対応など、既に発生した問題の法的解決を担います。
⑵ 社会保険労務士(社労士):労務管理の専門家
・具体的な業務:
「就業規則」の作成・変更、職員の「雇用契約書」の整備、社会保険・労働保険の手続き、育児・介護休業の申請など、人事・労務に関する実務と手続きを担います。
⑶ 行政書士:行政手続きと予防法務の専門家
・具体的な業務:
上記で挙げた許認可申請や届出を担い、法的な紛争や行政指導が発生しないよう、トラブルの芽を未然に摘む役割を果たします。
この三者は密接に関係しており、例えば行政書士が整備した院内規程が、社労士による労務管理の土台となり、万が一トラブルが発生した際には、それらの書類が弁護士の交渉材料となります。
これらの士業が連携し、医療機関を多角的にサポートする体制となります。
6 医療法務を行政書士に依頼するメリット
多忙な医療機関が行政書士に法務を依頼することで、以下のような具体的なメリットが生まれます。
⑴ 圧倒的な時間と手間の削減
院長先生や事務長が自ら関連法規を調べ、慣れない書類を作成する膨大な手間を省きます。
「あとは押印して提出するだけ」の状態まで整備するため、本来の業務である医療に集中できます。
⑵ 行政対応における安心感と確実性
行政書士は、県庁や保健所、厚生局とのやり取りに精通しています。
「この地域の保健所では、この点を特に重視する」といった実務的な知見を活かし、スムーズで的確な申請を実現します。
⑶ 医療業界に特化した専門知識
医療法務を専門とする行政書士は、診療報酬制度や医療業界特有の慣習にも明るく、単なる手続き代行に留まらない、経営に踏み込んだ提案が可能です。
⑷ ワンストップでの課題解決
当事務所は、弁護士、社労士、税理士など、他士業との強力なネットワークを持っています。
法務だけでなく、労務や税務に関する問題が発生した際も、適切な専門家へスムーズに繋ぎ、ワンストップで課題解決を進めることができます。
2 薬機法(薬局)関係
・薬局を開設する場合、行政から薬局開設許可を受ける必要があり、それには薬機法で定められた一定の要件を満たさなければなりません。
・また、薬局を開設するにあたり、薬剤師の資格を有する者が常時在籍していることが義務となっております。
・それと薬局の施設基準として、必要な面積や機能を備えた調剤室など、各種スペースの確保など、薬局としての環境作りが必要となります。
・そして重要な点として、医薬品の保管や管理についての規定類も整備し、遵守するひつようがあります。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。
3 薬機法(医療機器)関係
・薬機法(正式には、「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律」といいます)において、病院やクリニックなどで使われる「医療機器」について、厚労省、各県、保健所において、厳しい許認可関係があります。
・医療機器について、製造販売業、製造業、販販売業・貸与業、修理業といった区分があり、そのための許認可関係が定められています。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。
4 毒物及び劇物取締法関係
・薬局などで、毒物・劇物を販売する際には、毒物及び劇物取締法により、毒物劇物販売業の登録をしなければなりません。
・登録(保健所)には
1 一般販売業:全ての医薬用外毒物、医薬用外劇物を販売
2 農業用品目販売業:農業で使用するの毒物劇物を販売
3 特定品目販売業:規則で定められた品目のみの販売
を登録する必要があります。
・その許認可関係について、行政書士として対応します。
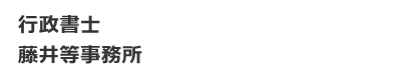






.jpg)